ホウセキキントキの保護色による変化の写真が撮れた
美しいピンクの魚体と金色に光る眼がとっても綺麗なお気に入りのひとつ、ホウセキキントキです。竹島水族館でこのホウセキキントキが追加展示されていました。

このサイトのWeb図鑑として先日記事にしましたが、ホウセキキントキは魚名判定にイマイチ自信が持てないと書きました。
→ ホウセキキントキ(2017年4月22日の記事)
その最大の理由が竹島水族館が掲示しているこちらの解説パネルの写真です。
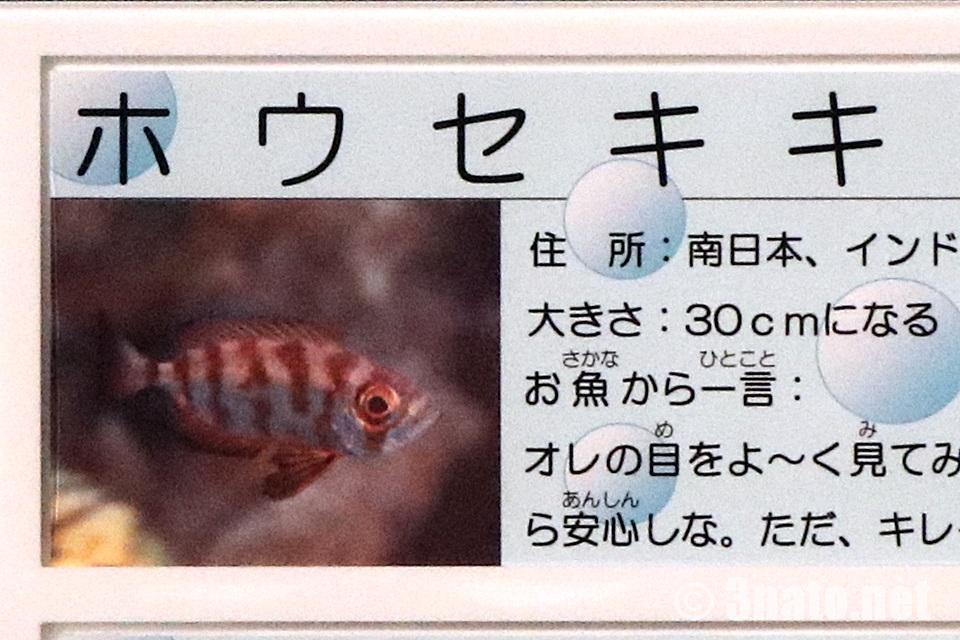
体側に帯のような濃淡のある紋様がある写真を見て「幼魚のうちはこんな紋様で成長するにつれ薄いピンク一色に変わっていくのかな。」と思っていました。
飼育員さんも忙しくて成長につれてパネルを作り直すのも大変だからずっとこの写真を使っているんだろうと思ってしまったわけです。
新たに何匹か追加されたホウセキキントキです。美しい魚体で泳ぐ姿に見とれてしまい、水槽の前をじっと動かずに眺めていたら「えっ?!。」という光景が。それが下の写真です。


ひとまわり小さな魚体は若いからだと思ったのですが、ふと岩の窪みに張り付くようなホウセキキントキを見てみたら帯の色が消えていくような、、、。

さらに暫く見ていたら体色が変化しているように感じました。それもわずか数分のことです。
「えぇ~ッ?!。」と思っていたら、こんな奴が目の前を泳いでいきます。

もうこの水槽から動けなくなり暫く観察を続けることに。といっても10分~20分程度で変化がわかりました。
下の3枚は同じ位置から撮った写真です。奥の岩に張り付き暗い位置に居るホウセキキントキに注目してください。



一部の生物やお魚は保護色という能力を持つことは知っていましたが、これほどはっきりわかる変化を初めて見た気がします。
岩肌近くの暗い位置を離れ、白い底砂のあたりに来たり、水槽ガラス面に近い明るい場所を漂うときには(薄い)ピンク一色に変化していきます。

今回保護色について調べていて、もう一つの特徴である金色に光る眼についての記述をいくつか見つけました。
これは網膜の後ろにタベータムと呼ぶ反射層によるのだそうです。通り抜けてきた光をここで反射させてもう一度網膜へ当てることでより明るく見える仕組みになっているのだそうです。
ホウセキキントキ以外でもキンメダイ、ハシキンメなど深度の深い場所に生息するお魚に金目が多い理由が納得できました。
外部リンク Wikipedia(保護色へリンク)
最終投稿日:2017/06/25

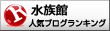


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません